この記事では医療情報技師試験の中でも、
医学・医療系の頻出箇所と勉強方法を解説しています。
細分化し記事にしており、
本記事は「医学・医療統計」についてです。
過去6年分(2018年~2024年・2020年は中止)の問題を筆者が分析し、
公式テキストに基づいて重点的に学習する箇所の解説を行います。
受験される方、
医学・医療系の学習が初めててでどこから手を付けていいかわからない!という方の参考になれば嬉しいです。
医学・医療系全般の攻略法についてはこちらで解説しています。
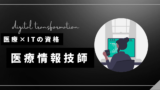
筆者について

第22回(2024年度)医療情報技師認定試験に初受験&独学で合格しました。
職歴は医療事務歴20年以上
現役で医事課に関係する業務サポート(日常業務・診療報酬請求)で複数医療機関での仕事と、
医療事務講師もしています。
保有資格は医療事務関連だけではなく、
診療情報管理士、医師事務作業補助者などもあります。
公式テキストについて
こちらのテキストを元に解説しています。
ページも記載していますので、
学習の参考にしてください。
※第7版のページを掲載しているため、
第8版をお持ちの方はページにズレがありますのでご注意ください。
医学・医療統計の出題傾向
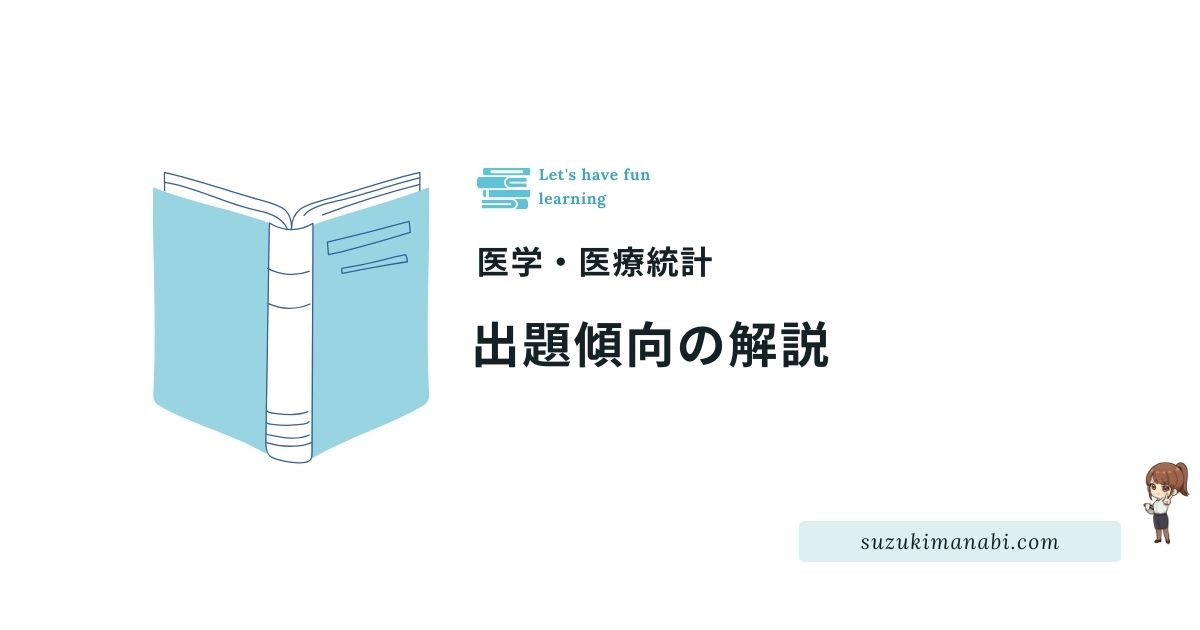 公式テキストでは441ページからの統計に関する問題です。
公式テキストでは441ページからの統計に関する問題です。
過去6年の出題数は平均して3問程度。
これまで統計について学習したことがない方には最初から理解していくのは難しい分野といえます。
医学・医療系は出題が50問。
過去の合格基準をみると50%程度でも合格できていることがありましたが、
2024年度は67.2%と高い水準となっています。
医学・医療系は、
医学、社会保障と医療制度に関する問題の出題数であわせて20問程度。
ここでしっかり得点できれば統計については学習が不十分でも合格を目指せます。
まずは頻出のポイントに学習を絞って、
余力があれば学習を深めていきましょう。
これまで統計の学習をしたことがある方にとってはそれほど学習する必要がない範囲ともいえます。
重点的に学習する箇所
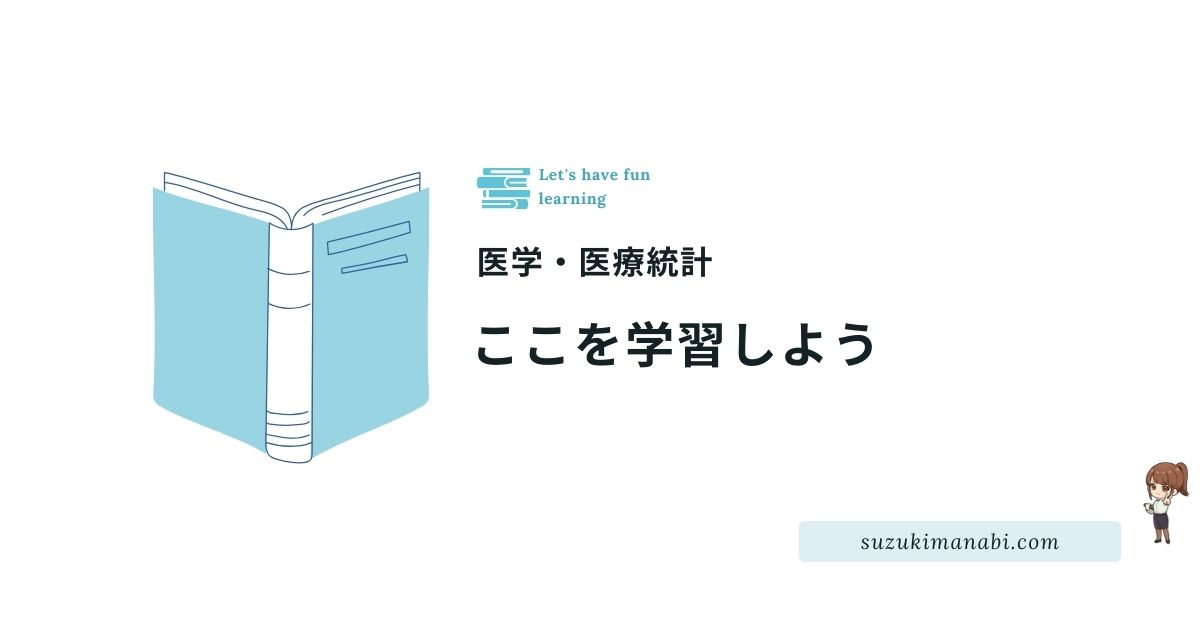
正規分布に基づく推定と検定
この範囲は過去6年で2022年を除き出題があり、
出題数は7問と、
圧倒的にこの範囲からの出題が多くなっています。
公式テキストでは452ページからで、
この中でも仮説検定(公式テキスト457ページ)に関する問題は過去6年で3問となっています。
正規分布の特徴をとらえ、
過去問題に出題されている内容をしっかり学習しておきましょう。
先にも書きましたが、
これまで統計を学習したことがない方が最初から理解していくことは難しい分野です。
受験までの期間、
学習量を考えれば深追いは禁物の範囲です。
過去問題中心の学習にし、
難しい時は無理せず後回しでいい分野となります。
統計の検定ではないと割り切って後回しにすることも合格のためには必要です。
変量
公式テキストでは443ページからの変量は、
過去6年で3問の出題です。
公式テキスト443ページ「表10.1.1変量の種類」をまずは学習しましょう。
変量の種類とその例の組み合わせに関する出題が
過去3問の出題のうち2問となっています。
2024年にも出題されていますので、
ここをおさえて過去問題に取り組んでください。
グラフの表現
公式テキストでは474ページで、
過去6年の間に3問出題されています。
中でも箱ひげ図についてが2問となっているので、
箱ひげ図についてしっかりおさえていきましょう。
まとめ
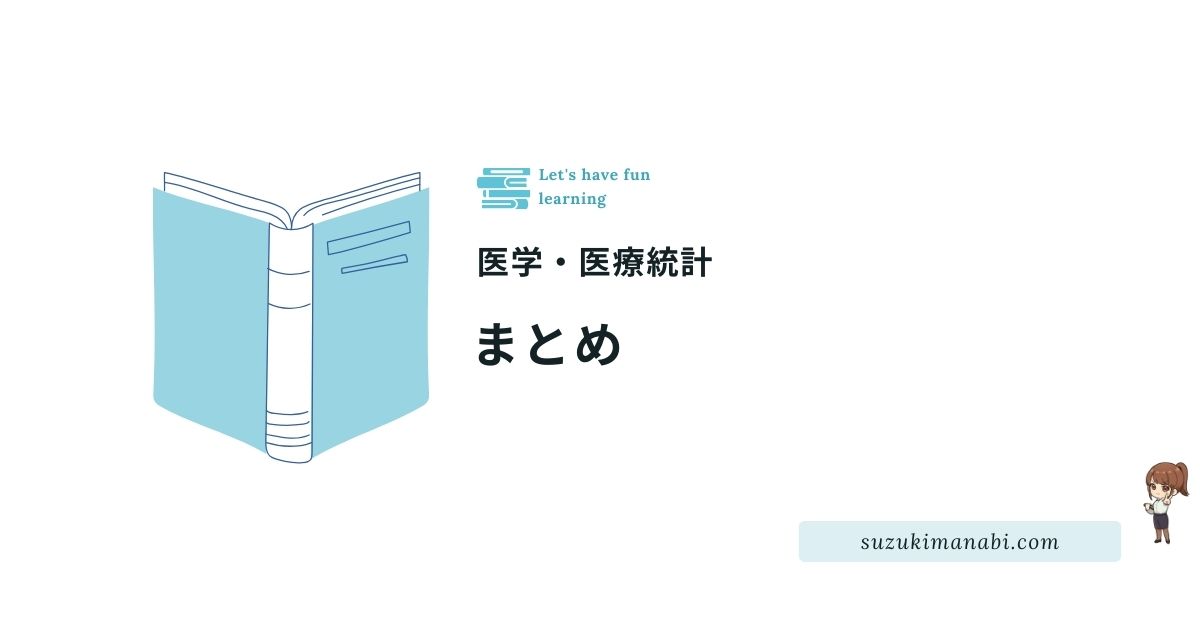
本記事では過去6年分の問題を筆者が分析し、
医学医療系分野の中から「医学・医療統計」について学習すべき箇所を解説しました。
これまで統計について学習したことがない方には最初から理解していくのは難しい分野といえます。
出題数は平均3問となります。
まずは過去問題中心に学習し、
余力があれば理解を深めていきましょう。
是非この記事の内容を優先的に学習し、
医学・医療総論分野の得点をしっかりとっていきましょう。
他の分野についても解説していきます。
また、X(旧Twitter)でも2025年度受験の方のために、
対策情報を随時ポストしますので是非フォローをお願いいたします!


コメント