この記事では医療情報技師試験の中でも、
医学・医療系の頻出箇所と勉強方法を解説しています。
細分化し記事にしており、
本記事は「検査・診断」についてです。
過去6年分(2018年~2024年・2020年は中止)の問題を筆者が分析し、
公式テキストに基づいて重点的に学習する箇所の解説を行います。
受験される方、
医学・医療系の学習が初めててでどこから手を付けていいかわからない!という方の参考になれば嬉しいです。
医学・医療系全般の攻略法についてはこちらで解説しています。
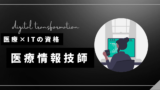
筆者について

第22回(2024年度)医療情報技師認定試験に初受験&独学で合格しました。
職歴は医療事務歴20年以上
現役で医事課に関係する業務サポート(日常業務・診療報酬請求)で複数医療機関での仕事と、
医療事務講師もしています。
保有資格は医療事務関連だけではなく、
診療情報管理士、医師事務作業補助者などもあります。
公式テキストについて
こちらのテキストを元に解説しています。
ページも記載していますので、
学習の参考にしてください。
※第7版のページを掲載しているため、
第8版をお持ちの方はページにズレがありますのでご注意ください。
検査・診断の出題傾向
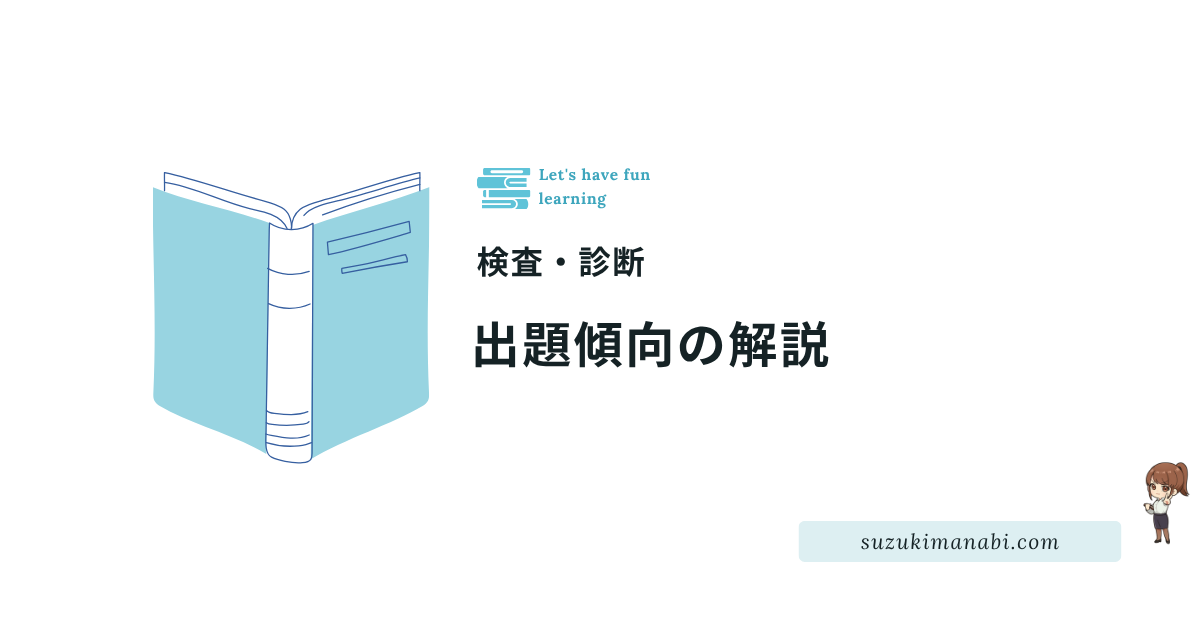 過去6年では1回に6~8問の出題。
過去6年では1回に6~8問の出題。
できるだけ落としたくない分野となっています。
テキストでは291ページから333ページで数が多いわけではないものの、
医療の知識がない人にとっては厳しい範囲となります。
というのも、
検査項目と病気の関連について問われる問題が多く、
医学に初めて触れる方にはイメージがつきにくくなっているためです。
重点的に学習する箇所
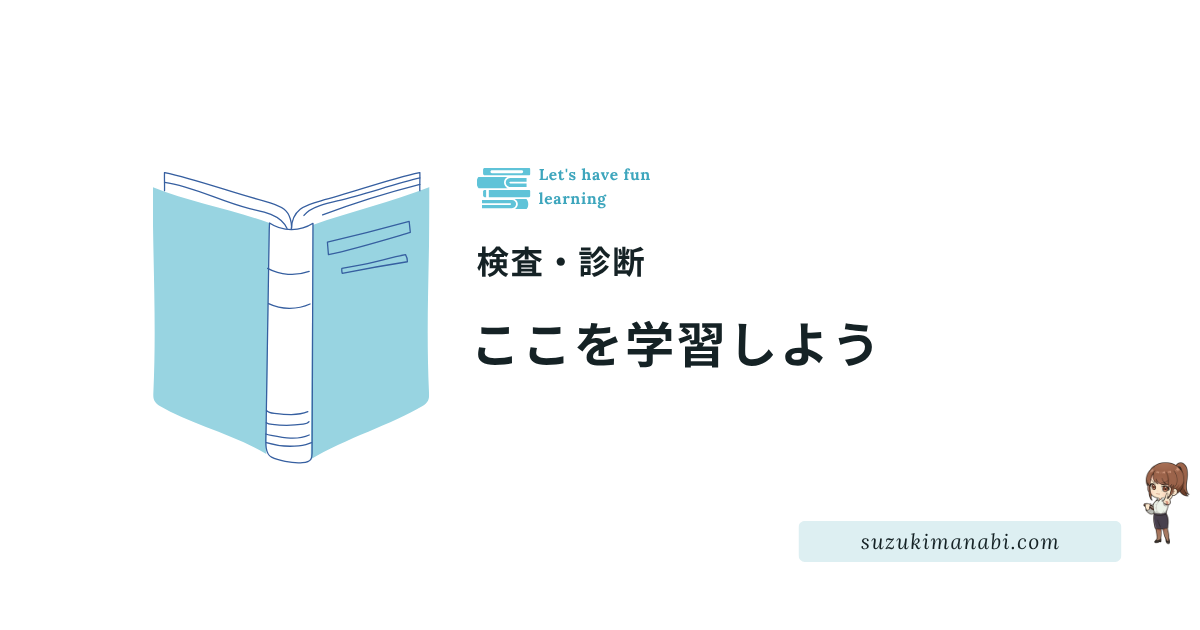
画像診断
過去6年で20問と、
圧倒的な出題率を誇る画像診断。
どのような検査となるのかを理解しておく必要があります。
超音波検査と内視鏡検査も画像診断に入っているため、
医療事務を学んでいる方はご注意ください。
(診療報酬では超音波検査と内視鏡検査は画像ではなく検査になるため)
絶対に抑えておくべき箇所は、
「放射線を使用しているかどうか」
MRIは磁気なので放射線ではないことなどを理解しておく必要があります。
検体検査
次に過去6年で出題数11問の検体検査も抑えておきましょう。
ここは深追いするとキリがないので、
過去問題に出題されている箇所を中心にテキストを読むことで対策していきます。
生理機能検査
テキスト303ページからの生理機能検査では、
過去6年で7問の出題。
2023年を除き、毎回出題がありますが、
やはり深追いはキリがない範囲。
テキストでも2ページちょっとなので、
過去問題とテキストを読む程度でいいでしょう。
まとめ
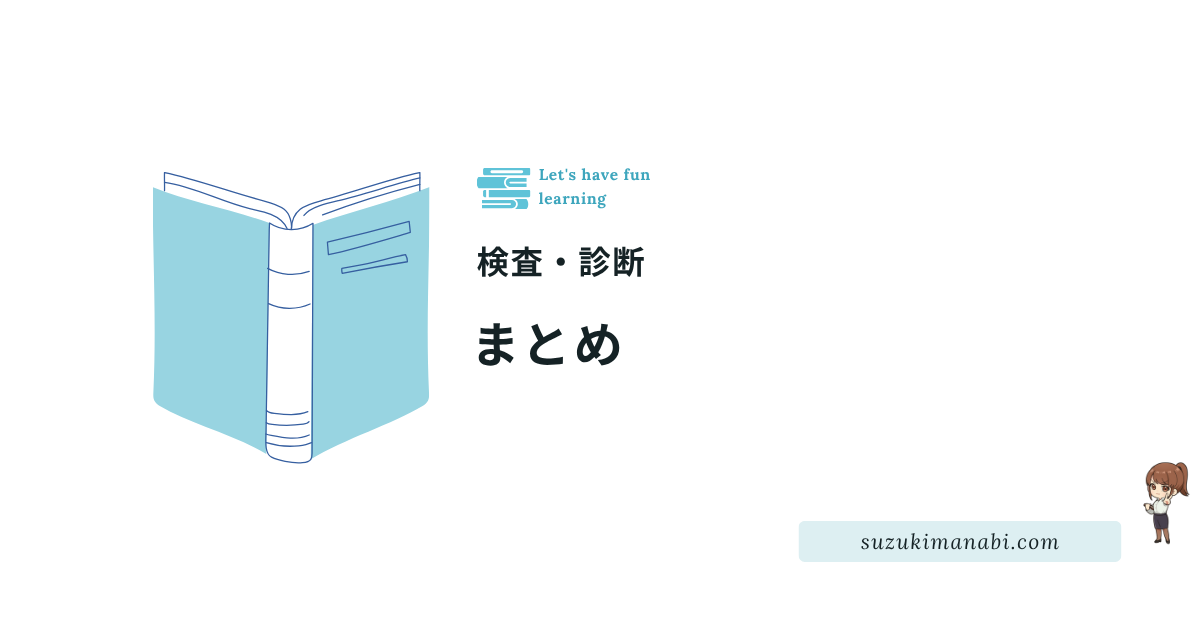
本記事では過去6年分の問題を筆者が分析し、
医学医療系分野の中から「検査・診断」について学習すべき箇所を解説しました。
この分野では画像診断と検体検査の出題数がかなり多く落としたくない範囲です。
しかし、深追いは禁物。
過去問題とテキストの範囲を読む程度に抑えつつ、対策していってください。
が中心となっています。
是非この記事の内容を優先的に学習し、
検査・診断分野を1つでも多く得点していってください。
さらに具体的な学習計画、試験直前の最終対策だけでなく、
医療情報技師の計算問題に特化した攻略、
「医学・医療系」の頻出テーマの解説は、
私のnoteマガジンで全て提供しています。
あなたの合格を全力でサポートするため、ぜひご活用ください!
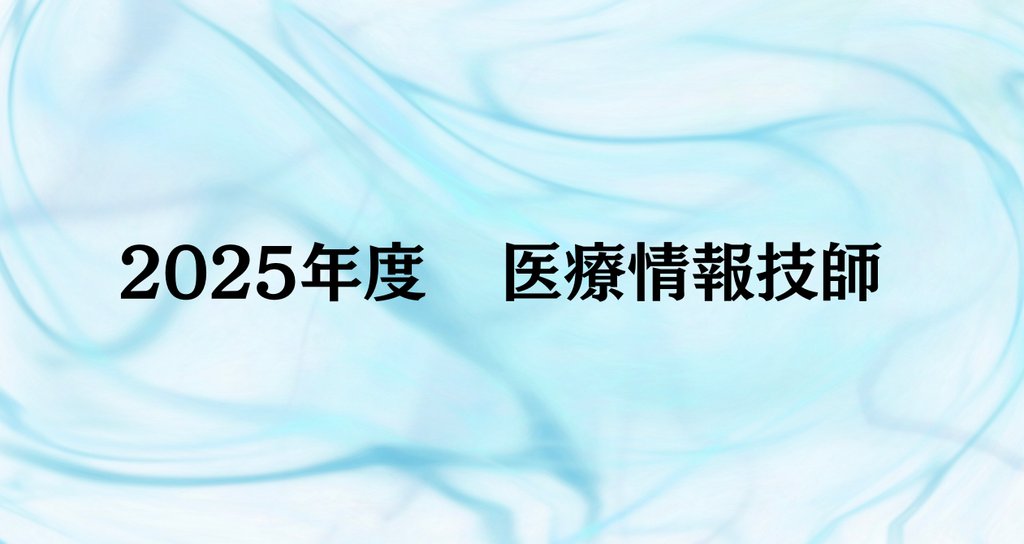
X(旧Twitter)でも2025年度受験の方のために、
対策情報を随時ポストしますので是非フォローをお願いいたします!


コメント